【事例紹介】海外での修学旅行の学びと生徒の進路-アジア研修での成長とは
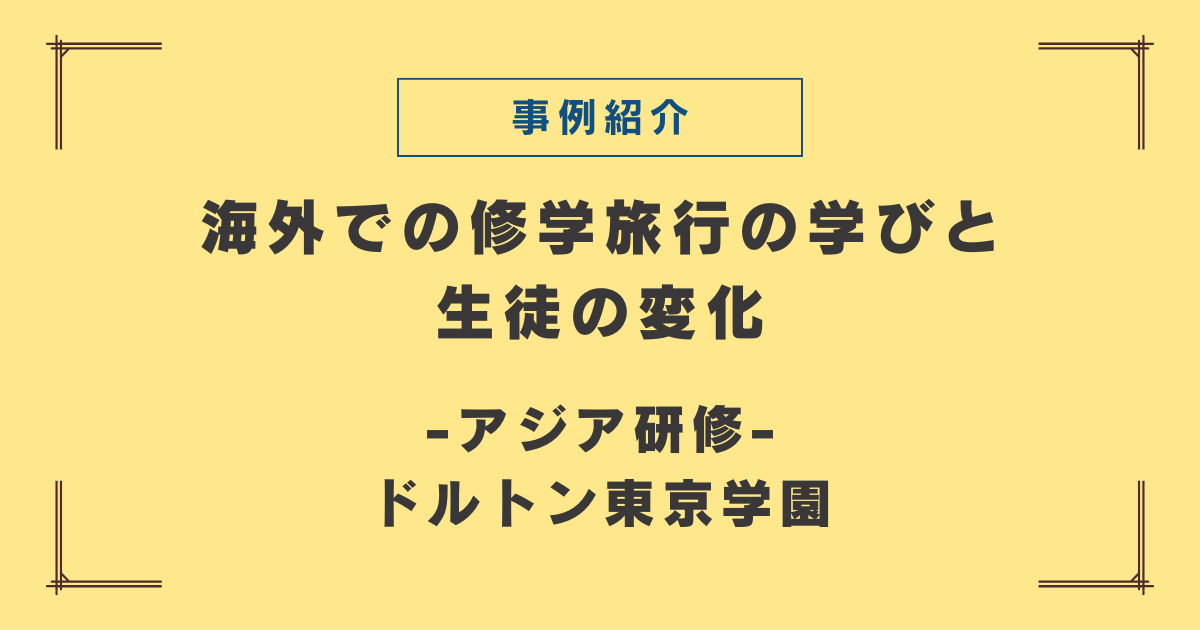
「修学旅行を学びのあるものに変えたい」
「海外で修学旅行をする事例を知りたい」
「評価方法や生徒の進路の変化を知りたい」
グローバルな学びが求められるなか、多くの先生方からこのような声をいただいています。
本当の意味で、学びのある修学旅行とはどのようなものでしょうか?
今回は、ドルトン東京学園の安居長敏 校長先生にお話を伺いました。アジア研修について、タイガーモブ代表・中村と、ざっくばらんにお話いただきました。
- 越境と内省を軸にしたドルトンの学びとは?なぜ海外で修学旅行を実施するのか。
- どのように修学旅行の成果を評価するのか。
- 参加した生徒たちの進路はどのように変化したのか。
学校の理念に基づいた、生徒の学びになる新しい修学旅行の形を知ることができます。
※この記事は、2025年1月10日に開催したイベント内容をまとめたものです。
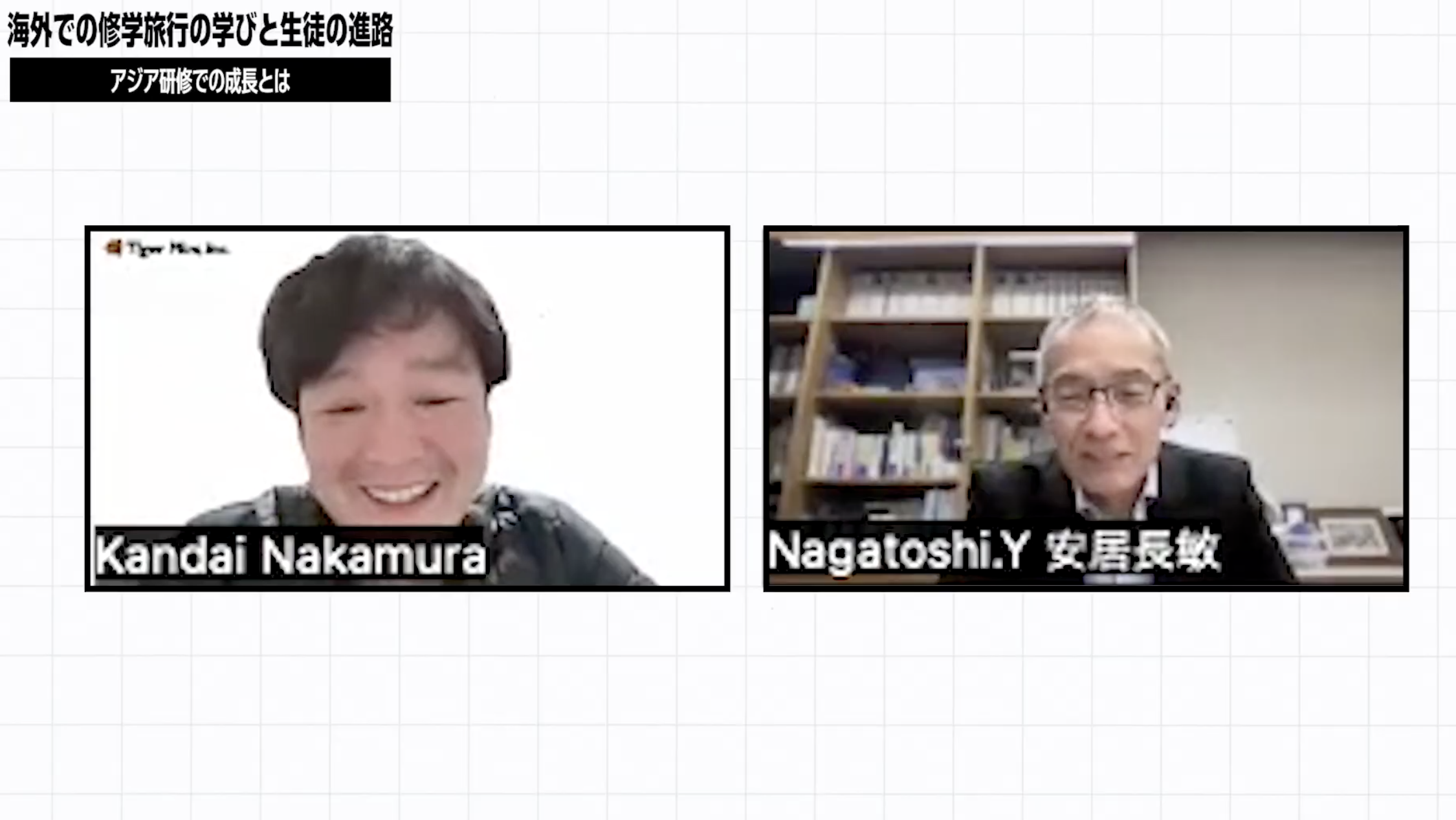
ドルトン東京学園でのアジア研修の位置付け
(中村)よろしくお願いします!まずは安居さまから、ドルトン東京学園での海外研修の位置付けについて教えていただけますでしょうか?
(安居さま)本校では、中学1年生から高校3年生までの6年間を通じて探究的な学びを展開しています。その中で、高校1年生のアジア研修は、それまでの学びの集大成としての位置づけです。生徒たちが3年次、4年次で大きく飛躍するタイミングに合わせて実施しています。
現在、本校では3つの全員参加の海外研修を実施していますが、高校1年生のアジア研修は、絶対に外せない行事となっています。タイガーモブさんと協力しながら、素晴らしいプログラムに育ててきました。
(中村)「恐れず進め」というドルトンの大きな理念に合わせて、アジア研修でも「恐れず進む場所」を選択されているという印象を受けました。では、実際にアジア研修をカリキュラム内でどのように位置付けているのでしょうか?
(安居さま)アジア研修は、実際の渡航は8月末から9月にかけてなのですが、4月から7月までの事前研修、そして帰国後から3月の成果発表エキスポまでの事後研修を含めた、1年間の長期的な学びのサイクルとして設計されています。
(安居さま)ドルトンの場合、1学年の生徒を4カ国に分け、各国約20人規模の少人数制で実施しています。この規模感は、生徒同士の対話を促進する上で非常に適切だと感じています。
各グループには教員が2名同行し、さらにタイガーモブのスタッフ、現地で訪問する企業の方々にもサポートしていただいています。生徒たちの相談相手として様々な大人が関わってくださる環境が整っているのは、とても良い点だと思います。
ドルトン東京学園でのアジア研修の特徴

修学旅行だからこその教員と生徒の関係性の構築
(安居さま)特筆すべきは、この研修を通じて生徒たちが教員の新たな一面を発見できる点です。
普段の学校生活では見られない教員の姿、例えば20人程度の小グループでの密な関わりの中で、生徒一人一人のことを深く考え、危険な状況でも適切に対応する教員の姿に、生徒たちは感銘を受けています。
このアジア研修は、通常の修学旅行のような予定調和的な行程とは異なり、例えば突然100人へのインタビューといった挑戦的な課題が与えられます。そうした場面での教員の的確なサポートやアドバイスを通じて、生徒たちは「大人が自分たちをしっかり見守ってくれている」という実感を得られるのです。
このような理由から、本校ではアジア研修を今後もさらに充実させていきたいと考えています。もちろん、希望者向けの他の国際プログラムも提供していますが、アジア研修は特に重要な位置づけとなっています。
学校とタイガーモブでブラッシュアップし続けるアジア研修
(安居さま)毎年、タイガーモブの皆さんと一緒にプログラムの改善を重ねています。参加教員による振り返りや生徒たちからのフィードバックをもとに、次年度のプログラムをブラッシュアップしていくサイクルが非常に良く機能しています。
今年の特徴的な点は、「自己変容」をキーワードとしたことです。
これまでは現地での課題解決に重点を置いていましたが、その前に、まず自分自身を深く知り、変化していく必要があるという認識に至りました。
また、教員側で「ヒーローズジャーニー(英雄の旅)」という考え方を共有し、日常とは異なる体験を通じて生徒の内面がどのように変容していくのかという視点を持って指導にあたりました。さらに、「ジャーナリング」、つまり常に振り返りを書き留めていく作業も重視しました。
また、上級生の経験が後輩たちに共有されていくのも、このプログラムの良さだと感じています。
研修を経験した生徒の話を身近で聞くことで、次の学年の生徒たちは「私たちはこうしよう」という具体的なビジョンを持てるようになります。
これは生徒間だけでなく、教員間でもしっかりと経験が受け継がれていっています。こうした継続的な学びの循環が生まれているのも、タイガーモブに深く関わっていただいているからこそだと思います。
アジア研修で見えた生徒たちの変化と成果
(中村)アジア研修を通じて、生徒たちにどのような変化が見られるのでしょうか。
実際の生徒からの反応として特に印象的だったのは、首都圏で生活するドルトン生にとって「格差・貧困」というテーマが非常に響いたことです。これは研修先の4カ国の選定や現地での活動フィールドにも反映されていました。
また、「ジャーナリング」を通じた学びの言語化も重要な成果でした。単に口頭で感想を述べるだけでなく、文字として記録に残すことで、日々の活動を振り返り、成長を実感できる材料となりました。
そして、「自己変容」という概念が生徒たちにしっかりと根付いていたことも大きな成果です。ただ漠然と「変わらなければ」というのではなく、1日1日の努力が自分の成長につながっていることを実感できていました。わずか1週間という期間でも、大きく成長できた時間として生徒たちの中に刻まれているようです。
(中村)本当にその通りですね。今年は生徒の皆さんにジャーナリングノートを配布したのですが、日を追うごとに書く量が増えていき、振り返りの内容も徐々に深まっていくのが印象的でした。
保護者からの不安の声は解消できる
(安居さま)当初、保護者の方々から「アジアは大丈夫でしょうか」という不安の声も聞かれましたが、実際に経験した生徒たちの様子を見ることで、研修の価値が広く理解されるようになってきました。
学校全体でも、年々の経験の積み重ねによって、このプログラムの意義が共有されてきているように感じます。
(中村)本当にそうですね。毎年改善を重ねて、ようやく現在の形にたどり着きました。私たちも一緒にプログラムを作り上げていく中で、多くの学びを得させていただいています。
修学旅行での生徒たちの変化を可視化して見えたこと
(中村)ドルトンではそのような変化を可視化しているそうですがどのようなものでしょうか?
(安居さま)本校では学びの成果を可視化する手段として、17のコンピテンシーを測定しています。
6年間の成長を可視化する学校として、アジア研修に関連する部分を抽出して分析してみると、興味深い傾向が見えてきました。
例えば、第一期生の中学から高校2年にかけての変化を見ると、コンピテンシー全体で20%以上の伸びが確認できます。
ただし、その伸び方には特徴があり、全員が均一に伸びる力と、個人差が大きく出る力があります。特に、アジア研修での学びは、個人差が出やすい項目に大きな影響を与えていることが分かってきました。
生徒の変化に最も影響する要素とは
また、生徒の成長パターンは大きく4つに分類できます。探究を中心に成長するタイプ、社会課題解決を軸に成長するタイプ、実行力で伸びるタイプ、チーム活動で成長するタイプなどです。それぞれの生徒の特性に合った成長のエンジンを提供することが重要だと考えています。
特筆すべき発見として、「共感・傾聴力」という項目があります。これは、当初の水準に関係なく、多くの生徒が著しい成長を見せる項目です。特に興味深いのは、当初低い水準だった生徒が、高水準だった生徒を追い越すケース、いわゆる「大逆転」が見られることです。
実際、共感・傾聴力が高い生徒は、7つの項目で大きな伸びを示しています。
さらに分析を進めると、この共感・傾聴力は「グローバル市民力」とも密接に関連していることが分かってきました。異なる環境や社会課題に向き合うことが、教育効果の向上につながっています。これはまさにアジア研修が目指していることと合致しています。
実際、生徒たちのジャーナルを見ると、グローバル市民としての意識の向上が見て取れます。その場限りの感想で終わらず、次の行動につなげる視点や、校内での活動(企業ゼミなど)と結びつけて考察するなど、より深い学びが実現できています。
(中村)経験学習が回り始めてますよね
(安居さま)そうですね。これらの分析から、共感・傾聴力を高めるためには、普段とは全く異なる環境での体験と、それをしっかりと振り返るプロセスが重要だということが分かってきました。
生徒の変化に最も影響する体験
特に注目すべきは、失敗体験の効果です。
現地での失敗体験がどれだけ共感・傾聴力の向上に影響を与えているか分析してみると、興味深い結果が出ています。失敗体験があったと明確に報告した生徒たちのデータを見ると、特に教育成長力などの項目で、失敗体験の有無による差が顕著に表れています。
(中村)そうですね。失敗をした時に「なぜこうなったのだろう」と考え、様々な人に話を聞きに行く、という行動がよく見られます。その過程自体が大きな学びになっているんですよね。
(安居さま)失敗についても、「こんなことできるはずない」と最初は戸惑いながらもチャレンジして、確かに失敗はするのですが、振り返ってみると良い経験だったと気付く。
そこで自分を見つめ直して、次はこうしようと考える。アジア研修の中でも、その日にできなかったことを翌日に再チャレンジしたり、形を変えて挑戦したりする機会があります。
特に夜の振り返りの時間で、一人一人が自分の経験を見つめ直すのは非常に重要です。しかも、それが自分だけでなく、家族のような関係性の中で「自分はこう思ったけど、どうだった?」といった対話ができる。
タイガーモブのスタッフの方々も含めて、常に相談できる環境があるのは素晴らしいと思います。
(中村)私たちのオフィスにもドルトンの生徒たちが来ていましたが、アジア研修から帰ってきた後の彼らの変化には本当に驚かされます。生徒たちの主体的な行動や、自分の将来についての真剣な姿勢を目の当たりにして、研修の効果の大きさを実感しています。
学校の教育理念に合ったプログラムを作り上げる
(安居さま)ドルトンの教育理念の根底には、「子どもたち一人一人が学ぶ力を持っている」という確かな信念があります。そこに大人が適切な支援を加えることで、より良い学び手に育っていくと考えています。
一人一人、学び方も違えば、深さもゴールも異なります。だからこそ、同じ物差しで全員を測るのではなく、それぞれの成長を個別に見ていく。そういう考え方が本校にはあります。生徒が自分の強みを見つけた時の爆発的なエネルギーは、まさにその表れだと思います。
アジアという環境で20人程度の小グループに分かれ、自分の力でサバイバルしながら、他者の助けも借りて現地の課題解決に取り組み、深い自己理解を得ていく。このプロセスは非常に価値があると感じています。
確かに、どの学校でもこういったプログラムを実施することへの不安はあるでしょう。「大丈夫だろうか」という声も当然出てくると思います。ですが、これまでの実績を通じて教員たちにも確かな自信が育ってきました。これもタイガーモブさんのおかげだと思っています。
アジア研修は普段は見えていなかった一人一人の力が発揮される場所
本校の特徴として、「これが最高の姿だ」という単一の理想像を示して、全員をそこに導こうとはしていません。その子の持ち味を最大限活かすことを重視していて、「100人いれば100通りの良さがある」ということを常に伝えています。
このような個性の違いが、アジア研修では非常にリアルな形で表れてきます。慣れない環境で様々な活動に取り組まなければならない中で、普段は見えていなかった一人一人の力が発揮される。
「この子がこんな力を持っていたのか」と、お互いの良さを改めて見直すような場面も多く見られます。予定調和的ではない環境だからこそ、そういった発見が生まれやすいんですね。そういった声をよく聞きます。
全員参加することに意味がある海外修学旅行
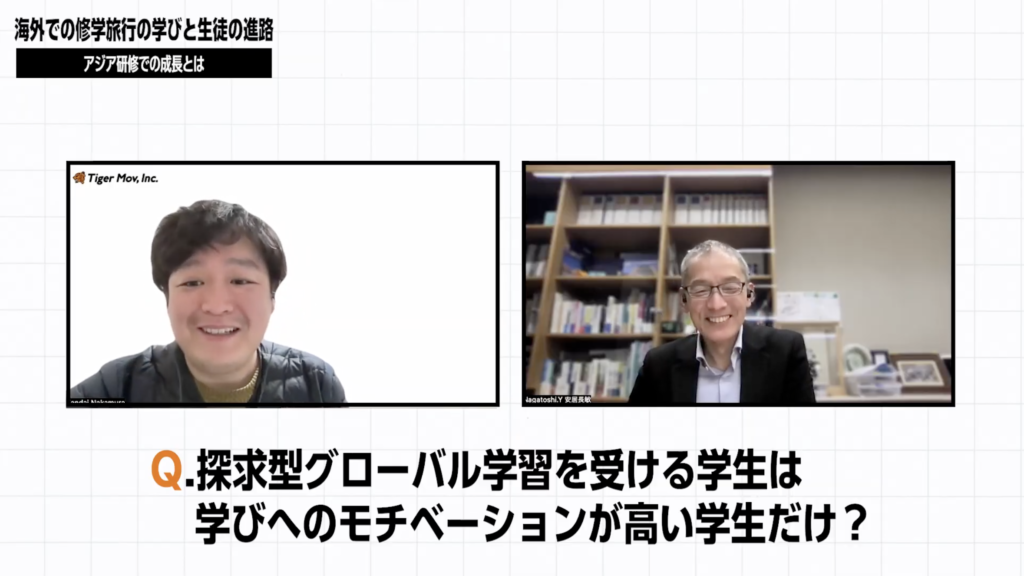
(中村)海外に慣れていたり意識の高い子だけが参加できるという訳ではないんですよね。実際、「海外には行きたくない」という生徒も少なくありません。「できれば飛行機は避けたい」とか、「日本語が使える国内で済ませたい」という声もあります。
ただ、興味深いのは、消極的な生徒たちが実際にプログラムに参加すると、むしろ大きな変化を見せることが多いのです。むしろそのような生徒の方が、きっかけをつかんで「君はどうしたらいいと思う?」といった対話を重ねていく中で、より顕著な変化を見せることを私は実感しています。
(安居さま)実際に生徒たちの中には「行きたくない」という声もあり、国の選択についても「やっぱりこっちの方が良かったかな」と迷いを感じる生徒もいます。
様々な不安を抱える生徒もいるのですが、事前研修を進めていく中で、その不安が徐々に解消されていきます。
最初は「しょうがない」という気持ちだったのが、次第に「自分でなんとかしよう」という前向きな姿勢に変わっていく。そういった自然な変化が見られるんです。
ですから、決して「できる子」や「モチベーションの高い子」だけのための活動ではありません。全員参加のプログラムですので、本当に様々なタイプの生徒が参加しています。
(イベント終了)
まとめ
今回はドルトン東京学園の安居長敏 校長先生にお話を伺いました。
これまでの修学旅行をよりよく出来ないかと考えていらっしゃる学校も多いと思いますが、ドルトン東京学園では、生徒一人一人の成長に焦点を当て、教育理念に深く根づいたプログラムを実施されています。
特に印象的だったのは、「自己変容」をキーワードに据えた学びの設計、そして全員参加型のプログラムとすることで、当初は消極的だった生徒たちにも大きな変化が見られるという点も興味ぐかかったです。
このようなプログラムの実現に向けて、私たちタイガーモブも引き続き尽力してまいります。
ご覧いただき、誠にありがとうございました。
他の学校・自治体の事例もぜひご覧ください。
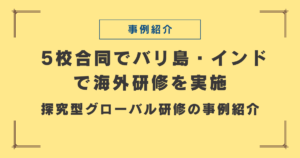
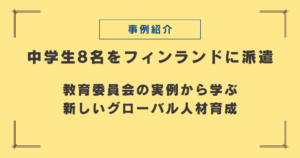
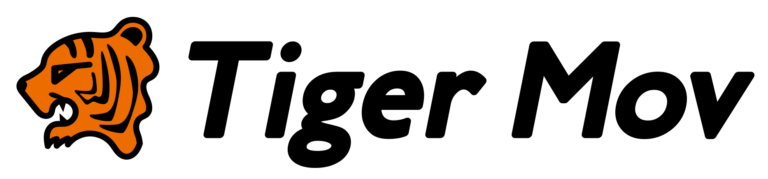
コメント